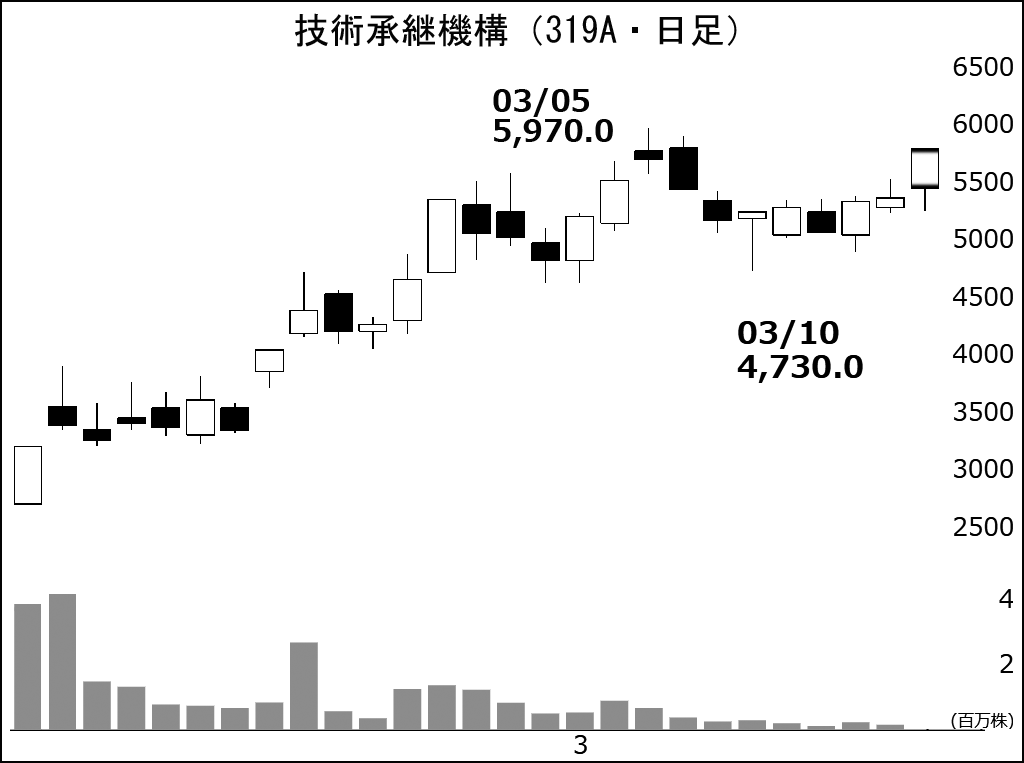2月5日に新規上場(IPO)した技術承継機構(319A・G)は製造業に特化した連続買収企業。ファンドでも事業会社でもない独自のポジショニングから、深刻化する製造業の後継者不足の課題を解消する存在として注目を集めている。上場という一大イベントを通過した今、同社にあらためて話を聞いた。
――IPOを無事終えた今の気持ちと今後の意気込み・抱負、現時点で実感している上場効果などがあればお聞きしたい。
今後も上場以前と変わらず適切なバリュエーションでの新規のM&Aと、譲受後のバリューアップの両輪を力強く回していくことで、右肩上がりの成長を継続していきたい。
上場の効果もあり、足元では紹介いただく案件が増えている。上場を通じて信用性や知名度が向上することによって、今後は譲受企業(グループ各社)における採用の促進や、売り主の方が安心して譲渡しやすくなるという点も期待できるのではないか。また、資金調達の選択肢も増えるので、より規模の大きな案件にも機動的に取り組めるようになる。
――譲り受けた会社が経営支援やバリューアップによって一定の成果を出すまで、どの程度の期間を要するのか。
バリューアップの取り組みに関しては、譲り受け~半年、半年~2年、3年目以降と3つの段階に分けている。段階的にそれぞれ効果的な成長支援を行っており、例えば初期の段階では譲受後すぐに効果が出るようなコスト削減の取り組みを施し、その後、採用や売り上げアップの施策などに取り組んでいくイメージ。
――上場を機にもう少し大きな案件、例えば上場企業のTOBなどにも挑戦していきたいと述べていた。近年はプライム上場の大手製造企業が買収攻勢を強める動きもあるが、将来的にこうしたところと競合になるのか。また、その際の御社の強みは。
将来的に競合になる可能性はゼロではないと思うが、前提としてそもそものポジショニングが少し違う。例に挙がった大手製造企業はどちらかと言うと統合志向が強いところが特徴であり強みと考えている。一方でわれわれは、あくまで各社の自主独立を重視している。独立性を尊重した上で、グループ内でのベストプラクティス(上手くいった事例)の横展開というところに注力している点が特徴であり強みだ。売り主の方から見ても、PEファンド(買収ファンド)でも事業会社でもない、新しい選択肢になっていると思う。
――政府によるM&A支援の動きをどう受け止めているか。
事業承継やM&Aの市場が盛り上がる、そこに追い風が吹くというのはすごく良いこと。国が後押しする=われわれのビジネスの社会的意義が大きいということの裏付けだと思うので、今後も愚直に事業を推進していく。
――前期決算(12月期)の振り返り、今期のポイントは。
前期に関しては当初計画から大きくぶれることなく着地できた。今期のポイントとしては、業績予想で示した数値に新規のM&Aの分は含んでおらず、あくまで既存10社の事業によるオーガニックの成長分であるというところ。今後、新規の譲り受けを発表させていただく際に上方修正ということがあれば、都度アナウンスしていく。(SS)